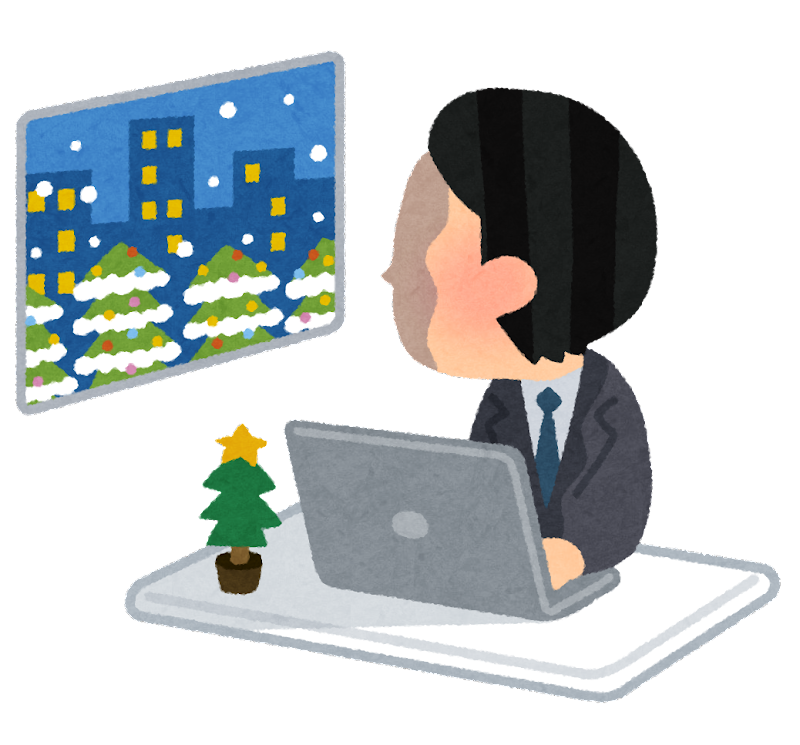することもしたいこともないから、毎日部屋のなかでじっとしていたら泥棒がきた。金目のものは全部盗まれ、服も脱がされてしまうと、この部屋で一番不要だった私が残った。することもしたいこともないから、そのまま毎日じっとしていたら隣人がきて、私をみて、「聖人だ」といった。どっちでもよかったので、そのままにしていたら、近所のひとたちが集まるようになった。それから毎日祈られた。朝祈り、昼祈り、夕祈られた。そして毎日捧げものをくれた。老人は金で、人妻は乳で、少年は尻だった。聖職者は性職者だった。欲望は捨て去っていたので、そのままにしていると、気づけば少年に手を出していた。少年の穴という穴を尻に変えて充填をしていると、少年は溺れ、死にそうな目をしていた。そのままにしていると、少年が私の細い腕をぐわしと掴むので、私は生きていることに気がついた。
「ああ。」
そのまま少年が成長して浅黒い肌をもつ男になり、財宝で飾られた私の首を、よく研がれた曲がった刀で掻き切ってくれることを夢想したが、現実は老人と人妻が結託して少年をダシに私を訴えることを私はよく知っていたので、私は逃げることにした。
「どこに行かれるのですか?」
「東のほうです」
東のほうにはここいらで一番高い山があって、あまりに大きいから近くにあるように見えるのだが、行ってみるとじっさい近くにあって登るのは簡単だった。山頂で振り返ると、近所のひとたちが麓までびっしり埋めていた。どうやら私の言葉を待っているらしい。癪だったので、無言で右手を空に向けてみると、彼らも無言で右手を上げた。そうやっておもしろがっていたら、突然雲行きが怪しくなって、空がピカッと光ると、かみなりが私を貫いた。私は黒焦げになって山頂に立っていた。これはなにかしらの罰なのだと思い、周囲を伺うと、例の少年が群衆のなかで気を失っていた。
「どうだ、まいったか」
私はそれだけ言うと、たましいだけになり、空に昇っていった。上から見下ろすと山全体が泣き声でどよめいていた。こんなに高いところは初めてで、私は少しめまいを覚えた。
「おえっ」
しかし吐くものがない
「おえっ」
しかし吐くものがない