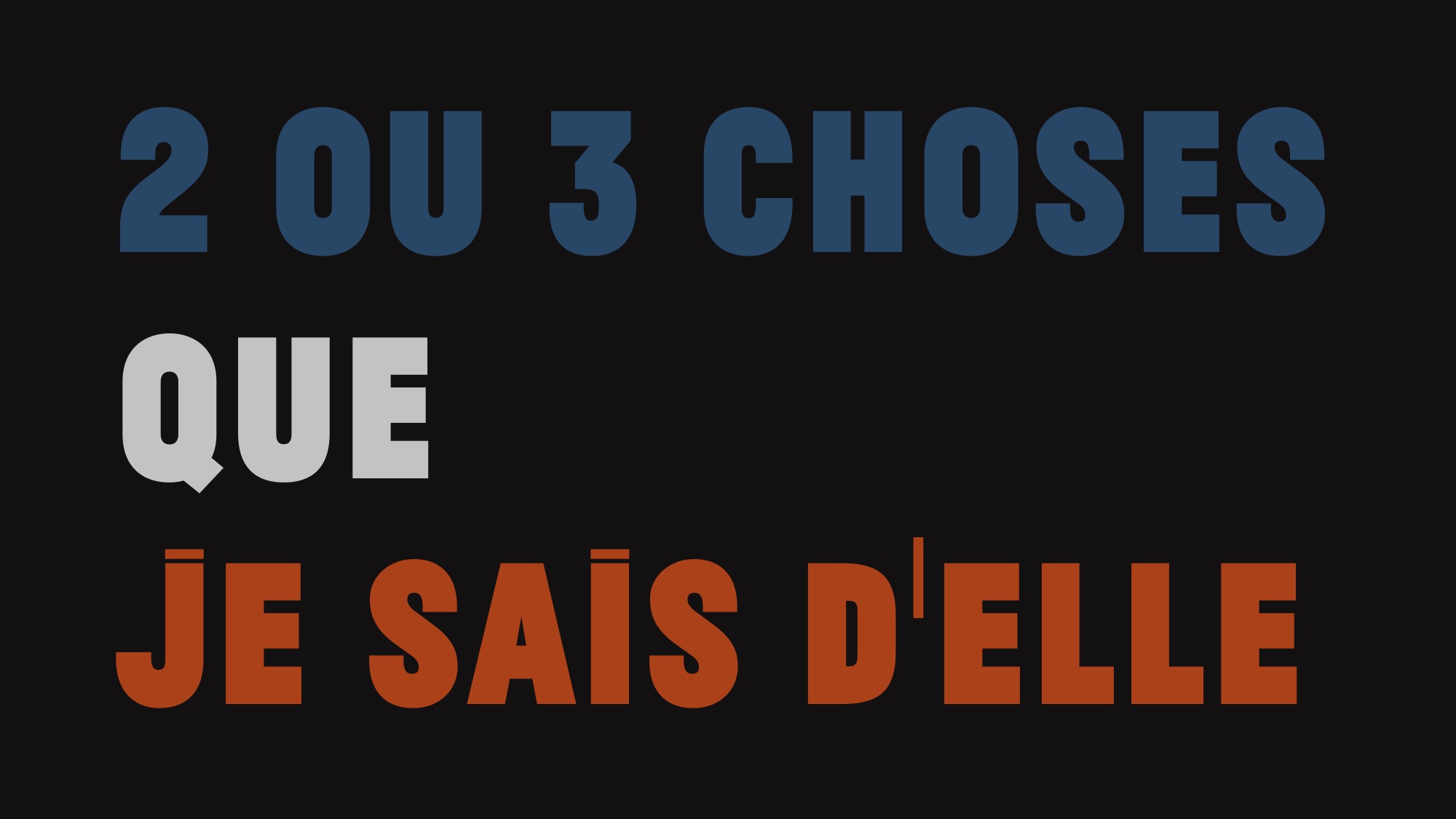映画『彼女について私が知っている二、三の事柄』をみんなでみました。監督はいわずと知れたジャン゠リュック・ゴダールです。
さて、これは映画レビュー企画なのですが、ひとによって解釈がわかれそうな映画をレビューすればおもしろいのではということで、いくつか鑑賞候補作品をさがしていて、わたしが最近はまっているゴダール監督の『彼女について私が知っている二、三の事柄』をみることになったのです。予告編をご覧になった方はもう気づかれたかもしれませんが、鑑賞してみた結果、よくわかりませんでした。レビューは以上です。いかがでしたでしょうか。
以下は、観賞後の座談会のもようです。わかったようなわからないようなことを長々と話しているだけですが、ここまでページをスクロールしてなおも読みたいという方はどうぞ。参加者は、おにもつ、ブヤコフ=マクシモヴィッチ、COLOR pencils、ヨシダガンジです。文末に、おにもつが書いた感想も掲載しています。
座談会
ヨシダ 今回の企画は、解釈が分かれそうな映画をみんなでみてそれぞれに感想文を書いてみようという趣旨だったけれど、映画の選択をミスって、解釈しようがない映画を選んでしまった。
おにもつ 僕はすべてを解釈したよ。この世のすべてを解釈した。
ヨシダ ……。この映画では文脈と関係なしに言葉が飛び出してくるわけで、その言葉はゴダールによる引用がかなりの量を占めていると思う。じっさいに別の本や映画からの引用だとあきらかなこともあるし、映画のなかでそこで発せられる言葉ではない言葉が引用されている。たとえば、女性がカメラのほうをむいて語り出す。言ってみたら、それは一般に理解されている映画の文法ではありえない。そこで説明される言葉も、ポストモダンの哲学書から出てきたかのようだ。それ自体が映画というもののなかにもうひとつ枠をつくって、そのなかに引用ができているというようなことを感じた。
おにもつ つまり映画というプロダクトのなかに入れ子になってプロダクトが存在するということを言いたいのか?
ヨシダ プロダクトという表現はキーワードだと思う。いまの言い方だと、ちょっと言いたいこととは違うけど。プロダクトとしての映画の代表はハリウッドの商業映画とかで、映画として求められるプロダクトがあって、そこで映画がつくられる。いっぽうで、この映画に代表されるようなものは、求められるプロダクトとしての映画ではない。映画という商品、求められるもののように見せかけて、なかに全然違うものを入れ込んでいる。なかに枠をつくるという言い方をさっきしたが、それよりは中身に全然違うものを入れ込んでしまっているということではないかな。
おにもつ ケーキ買ってきたと思ったら、饅頭入っていた。
ヨシダ そういうこと。
おにもつ ……ん?
ヨシダ ちょっと違うか。
おにもつ でも当時この映画を見にきた人は、何を求めて見にきているの? ハリウッドとかディズニーのようなものを求めているわけではないだろう。
ヨシダ それまでのゴダールの作品、たとえば『勝手にしやがれ』『軽蔑』『気狂いピエロ』、ああいう映画はまだちゃんとストーリーがあって、そうならざるをえないラストシーンがある。でもこの作品はそういうものを完全に破壊した。観客はそれまでのゴダールみたいなストーリーを期待していたと思う。ゴダールが意味わからんものをつくりだして、なんやこれはとなったのでは? 老舗の和菓子屋さんに行ったら、商品が変わって……
おにもつ とうもろこし茶。
ヨシダ それぐらい変わったんだと思う。
おにもつ 当時の広告の宣伝文とかどんなのだったんだろうか? 「巨匠ゴダールの問題作」みたいなのか、「夏はポケモン!」みたいないつもの感じを期待させたのか……。
ブヤコフ ゴダールとかのこういう感じの映画は、商業的に売れるものではない。だから爆発的にヒットするとか、マーケティングとか、そういう概念ではつくられていない。インテリとか、哲学的な知識がある人、60年代に起きたことに関心がある人たちとか。当時を経験した人であれば、そのときのリアルとその映画を照らし合わせて、知らない人間であればそのときの空気をそこから読み取って……。
おにもつ この映画は66年製作。
ブヤコフ これは66年にできた映画か。
ヨシダ つくられた当時の現在進行形で、ベトナム戦争もパリの都市開発もあったという状況。
ブヤコフ この映画は、ひとえに当時の思想と、当時のフランスを生きていた人間のリアルな世に対する認識とを散りばめたような詩的な作品だと解釈できると思う。ストーリーが明確にあるものじゃないから、むしろ詩に近い映画で、それを受け取れない人は受け取れずに終わっても仕方がない。ただ、詩は伝わる人には伝われと、言葉を投げるという営みであるという側面がある。遠いアジアのことでありながら、ベトナム戦争に否応なく関心を持たざるを得ない。そういうリアルは伝わってきた。
おにもつ たしかに映画としてみると訳わからんけど、動画付きエッセイだとすると、なるほどとなる。
ブヤコフ 詩的論理といったりするけど、そういう映画はたくさんある。タルコフスキーもそう。商業的な映画に慣れていたら、異質なものと映るだろう。
おにもつ 最近の映画はより多くの観客を動員して興行収入をどれだけ伸ばすかということに重点が置かれていて、それはSNSの発展でクチコミが広まりやすくなったからだろう。わかりやすいストーリー性だとか、伏線回収だとかを強化していく流れがある。そういうものばっかり見ていると、この映画はとても異質で、えっ!みたいになる。
ヨシダ ひとつおもしろいと思ったのは、終盤で「目とは何?」という問いに「見ることができているからそれが目だ」みたいなことを言っていて、そういうことなんやなと思った。この映画はけっきょくよくわからない。それが何か、何を意味しているのかがわからない。「それが何か?」と突き止めて問うことが、そんなに意味を持たないのではないか。ここで「意味」という言葉を使うと、それこそいろんな意味を持ってしまうから説明が難しい。「それが何か?」を問うことは重要ではなくて、そもそもそれが映像として「ある」ということだと思う。
ブヤコフ 「実存は本質に先立つ」ということだ。
ヨシダ 言葉で説明すると、言葉で説明されるものしか表現されないというか、言葉から想像されるものはあるけど、言葉がなければ何も出てこない。映像は、言葉がない状態で、カメラを適当に回したとしてもそこに映像は出てくる。そんなに映像と文章が違うかといえば、そこまで自信はないが。何を書こうとして無意識で書くことはほとんどできないが、映像をほぼ無意識につくりだすことはできると思う。
おにもつ ただあの映像は考えられて撮られていて、意識的ではと思った。
ヨシダ たしかに無意識で撮っているとは言い難い。
おにもつ 映像は下駄が高いという気はする。
ヨシダ ラストシーンで、「ハリウッド」と書いた雑誌かなんかが真ん中にあって、そこからズームアウトしていく。アメリカの大量消費・資本主義の象徴としてのハリウッドがあるわけ。ハリウッドの商業映画とは完全に決別するみたいな意思表示を映画全体でしていると言える。
おにもつ 反米、反資本主義、反商業主義という流れは一貫してあって、反資本主義を映画で体現していると思った。
ヨシダ ナレーションではっきり言ってしまっている。「テレビを買えば洗濯機を買えなくなり、洗濯機を買えば車を買えなくなる」みたいなこと。「洗濯機を買えば休みはなくなる」とか。それは正常な生き方ではない、ということを言っていたと思う。何かを得るために際限なく働き続けるというような社会の仕組みを批判的に表しているようだ。もうひとつは「LSDを買えなければテレビを与えられる」ということ。あれもインパクトがあった。テレビもLSDも、お金を払って快楽を得るというのでは一緒。
COLOR pencils 詩を書きました!
「わらってないね おなじだね」
わらってないねぇ
わらってないね
こんひとたちはわらってないねぇ
わらってないね
わらってないね
このひとたちはわらってないねぇ
おんなのひとのこえはやさしいねぇ
いもうとのこえはやさしいねえ
おんなのひとの目は目は目は目は目は
どこかにいるねぇ
ここにはいないねぇ
よくしってるねぇ
この目をした
こども
この目をした
こども
この目をした
おじいさん
この目をした
おとな
この目をした
お父さん
この目をした
この目をした
この目をした
わたし
しってるねぇ
ここにいるねぇ
しってるねぇ
わらってないねぇ
あおぞらはないねぇ
あおぞらはないねぇ
くもっているねぇ
くもっているねぇ
くもっているねぇ
わらっていないねぇわらってないね
こどもはなくね
こどもはなくんだねぇ
こえはこえは
てんき
こえはこえはてんき
こえはこえはてんき
くもっているねぇおあぞらはないねぇ
くもっているねぇ
つかれてしまうね、つかれてしまうねぇ
つかれてしまうねぇ
わからなじゃいねぇ
ことばについて
おなじだねぇ
かんさつについて
おなじだねぇ
きについて
おなじだねぇ
コーヒーについて
おなじだねぇ
右をよくみるんだって
左をよくみるんだって
同じだねぇ
やさしいねぇやさしいねぇ
やさしいねぇ
やさしいようでしんどいね
世界はわたしだね
ぬけだせないね
息苦しいねぇ
しってるねぇ
とおい人のことをかんがえる
ふしぎだねぇ
おなじだね
ぼくら
ぼくらぼくらともに
いっしょにかんがえることばはすきなんだって
ともにともにともにともに
すきなんだって
すきなんだって
本をよくよむんだって
本をよく読むんだって、
本をよく読むんだって
本を本を本を
よく読むんだって
おにもつ ……令和のゴダール?!
ヨシダ 論理で何かを問うことに意味がないとき、いまみたいなのはひとつの有効なやり方だと思う。
COLOR pencils 自分の命と向き合ってつくったものが作品になると、それに対して自分も命を出すというのがしっくりくるかな。批評・分析も表現のひとつだけど。時代背景なんかはわからない分、ほかのところに意識を向けるというか。ペンキを塗ってるおじさん、わかる? 橋のところで。ほかにも、最初のシーンで手押し車があったのとか。子どもの泣き声とか。
ヨシダ 子どもということでいえば。「同志愛について」という作文を読み上げる子ども。あれもあの歳の子どもがあれを書くわけがないだろう。
おにもつ あれはあの子が書いたのか?
ヨシダ あれは違う? ほかにも、最初に夢の話をしていた。夢のなかで双子が合わさって、それは南北のベトナムが統一されたのだというような話を子どもがする。なに言ってんねんという感じだが、それは最後の作文にも共通する。あれもその子が書いたのだと思う。では、ああいうことを子どもが言ったり書いたりすることを見て、どう思ったか?
COLOR pencils 気持ち悪いと思った。子どもに言わせるのがありありとわかってしまう。そういうやり方こそがプロパガンダという矛盾……?
ブヤコフ アルジェリア難民の話も、子どもによる語りだった。「アルジェリアよりもフランスのほうがいいですか?」という問いに「悪い」と答えていた。あれはポストモダンだと思った。フランスのほうが進んでいるだろうが、そこに来た人間は必ずしも「いい」とは言わない。
おにもつ フランスのほうが嫌だと言っているのは、コンクリートジャングルで、お金がなければ、経済成長下の環境は生きにくいのだろうと思った。
ブヤコフ 混乱を逃れてきたにもかかわらず、フランスのほうが悪いという。帝国主義的な何かに対する批判はポストモダン的。
ヨシダ 少年の話にもどすと、未来の人間についての本を夫が読んでいる場面があって、未来の人間は判断力が優れていて……という理想化された人間像が出てくる。あの歳で子どもとしてはおかしい発言をしている子どもと、その理想化された未来の人間像が少し重なる印象を持った。そして、その本を妻は受け入れられないと言うと、夫は受け入れたくなければ他の本を読めばいいと返す。いろんなメタファーが出てくるが、それはゴダールの意図を直接表現するものか、皮肉なのか、解釈しづらいことがある。
(その後、さらに批評する立場に立つためには形式としての芸術を理解したいという話、知識を得ることで視点が広がるという話がありました。なお、この映画観賞会・座談会は2021年4月5日に開催したものです)
おにもつの感想
なんもわからん ああなんもわからん なんもわからん
なんもわからないということだけがわかった。
昨今の映画製作現場、特にアメリカのハリウッドでは商業主義が我が物顔で跳梁跋扈している。より多くの観客を動員し、興行収入をいかに伸ばすかに重点が置かれている。特に「わかりやすいストーリー」「登場人物の感情理解の容易さ」「出演者の知名度」「伏線回収の快感」など口コミでの拡散を促す要素を重視する流れは年々強まっている。SNS等の登場以来、この潮流はさらに加速し続けているといえるだろう。
最近の有名どころの映画しかかじってこなかった私としては、やはりこれまで見てきた「映画」との差異に驚くばかりであった。ブヤコフ氏が指摘した通り、この映画は60年代フランスの美しい映像をバックに、ゴダール氏の短い「詩」(と呼ぶべきか「エッセイ」と呼ぶべきかはわからないが)が詞華集のごとく描かれていく構成であり、一般的な映画の構成とは大きく異なる。教養のない私ににとって「詩」の内容はちんぷんかんぷんであったが、とかく米帝とそれに伴う商業主義を一貫して批判しているように感じた。商業主義を追究することで広がる貧富の差についてこの映画はクローズアップしていたように思う。この映画の舞台となった60年代フランスの団地では、都市の経済成長が続き人々がコンクリートジャングルに集まってくる一方、末端労働者の収入は雀の涙である金の回らない高度経済成長のような雰囲気を感じた(あれ……令和日本…?)。
『彼女について私が知っている二、三の事柄』が前述した商業主義にまみれた映画と一線を画しているのは明白である。90分通しで見ても何一つわからなかったため、「こんなの一部の映画マニアにしかウケないだろ!」というのが見終わった後の率直な感想であった。だが、この感想を持った私はすでに商業主義に迎合しており、それを無意識のうちに何食わぬ顔で受け入れているのである。反商業主義のゴダール氏の批判の矛先は実は前述の感想を抱いてしまった私にも向いているのではないだろうというのは考えすぎであろうか。
とにかく、ゴダール氏の思想である反商業主義をこの映画の構成は自ら体現していると捉えられる。
無自覚に商業主義に首を垂れている自分に気づかされたのと同時に、映画という枠で表せる表現の広さを体感し、映画の懐の広さに気づくことができた、とても有益な鑑賞会であった。