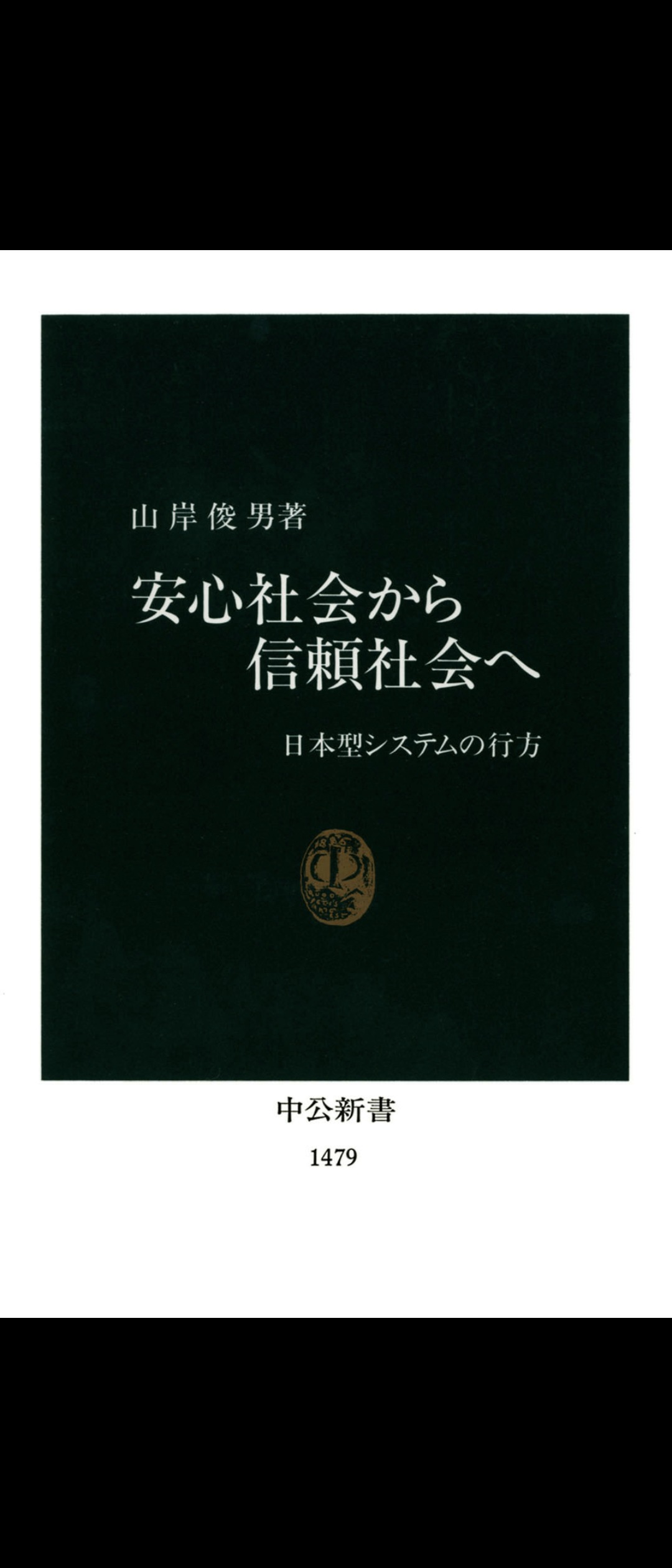先日、この著作を読んだ。
種々数々の統計的な社会心理学実験とその結果に基づき、日本人と欧米人との行動原理の差異、またその行動原理の差異を生み出しているそれぞれの社会における社会・文化的環境の差異を明らかに提示する事で「日本社会と欧米的な社会との文化的な裂け目を科学的・実証的に描き出す」事に見事に成功している大変な良著であった。本書の白眉たる部分を以下に纏めておきたい。
先ず「社会的知性」と言う概念が定義される。社会的知性とは「社会的な適応課題を解くために必要とされる能力」を意味するが、分かりやすく平たく言ってしまえば「人間関係を認知しそれを処理・運用する能力全般」の事。
そして次に、厳密な社会心理学実験の結果によってこの社会的知性が更に、それぞれほぼ独立に存在している二つの側面(能力)に細分化できる事が統計的に示唆される。
先ず一つが「人間性検知能力」、これは「相手の一般的な人間性即ち信頼できる人間かどうかを見抜く能力」であると定義される。
もう一つが「関係性検知能力」、これは「集団内での人間関係に敏感に気づく能力」であると定義される。
即ち社会的知性には「人間性検知を核とした社会的知性」と「関係性検知を核とした社会的知性」の二つが存在し、そしてこれら二つの能力はどうやら「それぞれ独立の」物である、と言う事が実験結果によって示される。
又この「社会的知性」と関連する物として本書の中で扱われる重要な概念に「一般的信頼」があり、これは「家族や狭い仲間うちを超えた他者一般に対する信頼」を意味する。様々な実験の中で、一般的信頼尺度と呼ばれる指標によってある人が「家族や狭い仲間うちを超えた他者一般をどのくらい信頼しているか」と言う事が測られ定量化される。
そしてこの「一般的信頼」と上記二つの社会的知性との間には以下の様な関係が見られる事が実験データによって明らかになる。
『人間性検知能力の優れた人は一般的信頼の程度が高く、他人との関係に対して楽観的な態度を持っているのに対して、関係性検知能力が優れた人は、あまり親しくない人との関係を避けようとする社会的びくびく人間である』(本書P178より引用)
これらの実験結果の示す大変興味深い所は先ず第一に、例えば私達がある人間の「人格の豊かさ」なるものを考える際には一般的に、その人間の持つ「他者に対する共感性の高さ」を重要な指標とする様に思われるが、しかし「相手の一般的な人間性即ち信頼できる人間かどうかを見抜く能力」と「集団内での人間関係に敏感に気づく能力」と言う、素朴に考えればどちらも同じく他者への共感性の高さによって規定されるかに見える二つの「能力」が実はそれぞれ独立に(一方の能力が高ければ他方も高い或いは一方が低ければ他方も低いと言う訳では必ずしも無い形で)存在していて、それ故ある人間の「人格の豊かさ」或いは「共感性の高さ」と言った属性を考える場合に私達はそれら二つの側面を混同させる事無く区分しなければならない、と言う点にある。
そして更に意外な事には、高い「関係性検知能力」即ち「集団内での人間関係に敏感に気づく能力」の持ち主は寧ろ、他者に対する共感性が低い傾向にある、と言う事が指摘されるのである。
その事に着目する事の重要性は、本書内で著者が以下の様に繰り返し繰り返しその点に言及している事からも明らかである。
『常識的に考えれば、集団内で誰が誰に対して好意をもっているか(この実験の場合には誰が自分に対して好意をもっているか)を正確にわかっている人は、そうではない人に比べて孤独感を感じることが少ないように思えますが、実験の結果はこの常識的な予想とはまったく逆の結果となっているからです。
同様に常識と逆の結果は、共感性や感情表出に関する質問に対する回答にも表れています。常識的には集団内における人間関係を正確に把握している人は他人と共感する傾向の強い人であるように思えますが、実験の結果はこの反対の傾向が存在していることを示しているからです。すなわち、関係性検知が正確であった人たちは「愛の歌や詩に感動しやすい」という項目に否定的に答えていると同時に、「私はまわりの人が悩んでいても平気でいられる」、「私はいつも感情を顔に表さない」という項目に肯定的に答える傾向を示しています』(本書P183〜184)
『関係性の判断が正確な人の人間像について、常識とは違った内容が示唆されています。常識的に考えると、集団内の人間関係や誰が自分に対して好意を持っているかを正確に認知している人は、いわゆる「よくできた人」で、他人に対して高い共感性を示し、対人関係に不安を感じることなく積極的に対処し、その結果、他人との間に親密な関係を築いている人のように思われます。しかし実験の結果は、この常識とまったく反対の関係を示しています。すなわち、関係性の判断を正確に行っている人たちは、他人に対する共感性が低く、対人関係に不安を感じており、対人関係に積極的に対処できず、孤独感を感じている人たちだという結果です。集団の中での対人関係を正確に理解する人たちは、いつもびくびくしながらまわりの人たちの顔色をうかがっている人たちでした』(本書P184)
では何故、一見常識に反したその様な実験結果が示されるのかを巡って山岸俊男氏は「この点についてはまだ十分にデータが蓄積されていないのではっきりした結論は避けるべき」だとした上で「好意の認知は共感を必要としない可能性を示すものだと考えられる」、「つまりある人間が他の人間に対して好意をもっているか嫌悪感をもっているかに気づくためには、その人の身になって感じたり考えたりする必要、つまりその人に対して共感を感じる必要はないからではないか」と言う極めて示唆深い仮説を提示する。その仮説について論じられているのが以下の部分である。
(本文P189〜190より引用、「地図型知性」は「関係性検知能力」と同義)
『自分が相手の立場だったらどう感じたり考えたりするだろうと思うのが共感するということですが、相手が自分に対してもっている感情や態度を推測するためには、そのような共感はあまり必要ありません。表情やそぶり、声の調子などのいわゆるノンバーバル・コミュニケーションの手がかりを正確に判断する能力があれば、相手がもっている感情や態度を推測するのに十分だからです。むしろ相手に対して共感を感じることは、相手の表情やそぶりなどから相手の感情を読みとる能力を阻害してしまうのかもしれません。
関係性検知の正確さと共感性との間のマイナスの関係は、この可能性を示唆しています。つまり、地図型知性の持ち主は、他の人たちの立場に身を置き、他の人ならどう感じたりどう思ったりするだろうという他者との認知的共感ないし(社会学の言葉を使えば)役割取得を使ってではなく、表情などのかたちで外部に漏れだした、相手の内面についての情報を使って対人関係の性質を判断するのが得意な人たちだという可能性を、この結果は示唆しています』
この点については最後にもう一度触れたい。
本書の第二章のタイトルは「安心の日本と信頼のアメリカ」であるが、この章の中では「アメリカ人の方が日本人よりも一般的信頼の程度が高い」と言う統計データが提示されている。前述した、一般的信頼の程度と人間性検知能力の高さが相関傾向にあると言うデータと突き合わせると、「アメリカ人の方が日本人よりも一般的信頼の程度が高いと言う事は、人間性検知能力の程度もアメリカ人の方が日本人よりも高い」であろう事が推測できる(但し人間性検知能力の日米差を比較できる実験結果は本書で紹介されてはいない)。
又、関係性検知能力の日米差を比較できる実験結果も同じく本書では紹介されていないが、「関係性検知能力と人間性検知能力とでは、それらが適応的な役割を果たす社会的環境の性質が違っている」事が論じられており、一般的信頼の程度に見られる日米差(そしてそこから更に類推される人間性検知能力の程度に見られるであろう日米差)は「アメリカと日本との間の社会的環境の性質の違い」によって説明可能である事が示唆されている。
よって、日本においてはアメリカに比べて「関係性検知能力の高さがより適応的な役割を果たす社会的環境の性質が存在して」おり、それ故に関係性検知能力の程度は人間性検知能力の程度とは逆に日本人の方がアメリカ人よりも高いのではないか、と言う仮定も又論理的に類推される。
そこから、二つの社会的知性の側面の内「人間性検知能力がより適応的な役割を果たす社会的環境の性質を持つアメリカ」と「関係性検知能力がより適応的な役割を果たす社会的環境の性質を持つ日本」と言う対比が導かれる(「安心の日本と信頼のアメリカ」と言う図式もその対比に重なる)。
そして1990年代末に出版された本書の終章は、社会的諸条件の変化に起因し従来までの集団主義的な組織原理に依存した日本的な社会システム(安心社会)を維持する事が最早困難かつ非合理な選択となってしまっている以上、欧米流の民主的で開かれた社会システム(信頼社会)への転換を日本は図るべきであり、
その為には「関係性検知能力は集団主義的な社会で適応的な役割を果たし、人間性検知能力は開かれた社会で適応的な役割を果たすと考えられる」事、及び「人々の適応行動とその行動を適応的にしている社会的環境との間には相互強化関係が存在している」事その二点を踏まえながら、人間性検知能力がより適応的な役割を果たす様な欧米流の民主的で開かれた社会システムへの移行を図って行くべきである(具体的な方策として、公的活動に関する情報開示と意思決定過程の透明化と言った手段が挙げられている)、
と言う著者の提言(=安心社会から信頼社会へ)で締め括られている。
以上本書の概略を見た上で、「高い関係性検知能力の持ち主は寧ろ他者に対する共感性が低い」と言う興味深い実験結果に対して山岸氏が提示した「ある人間が他の人間に対して好意をもっているか嫌悪感をもっているかに気づくためにはその人に対して共感を感じる必要はないからではないか」と言う仮説に再び戻り、「関係性検知能力が適応的な役割を果たす日本型安心社会と人間性検知能力が適応的な役割を果たすアメリカ的信頼社会」と言う文脈も重ね合わせながらそこで述べられている事のエッセンスを改めて抽出すれば
「認知的共感や役割取得の様に主に言語依存的な情報処理によって対人関係が認識・知覚され営まれる傾向にある欧米社会に対して、表情や仕草等のよりノンバーバルで非・言語依存的かつ”五感依存的な”情報処理によって対人関係が認識・知覚され営まれている日本社会」
と言う形になるのではないか。
勿論この考察の元となる「ある人間が他の人間に対して好意をもっているか嫌悪感をもっているかに気づくためにはその人に対して共感を感じる必要はないのでは」と言う山岸氏の指摘への充分なデータの裏付けは本書では示されておらず、それ故これらは飽くまでも仮説の域を出ていないとは言え、
それでもそこには西欧的な文化・社会と日本的なそれとの間にある根底的な差異について思索する為の重要な手掛かりが見つかり得るのではないかと思う。